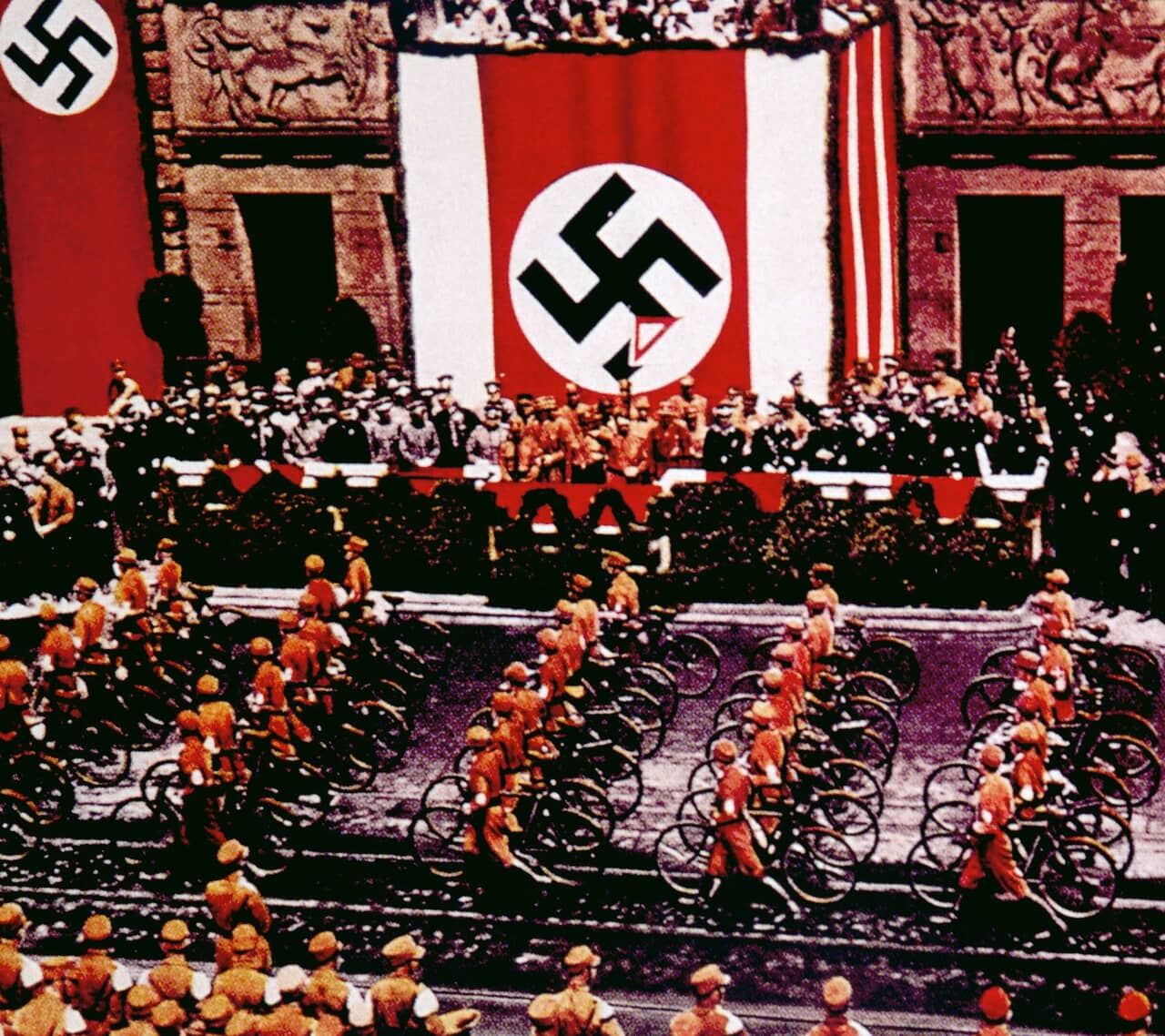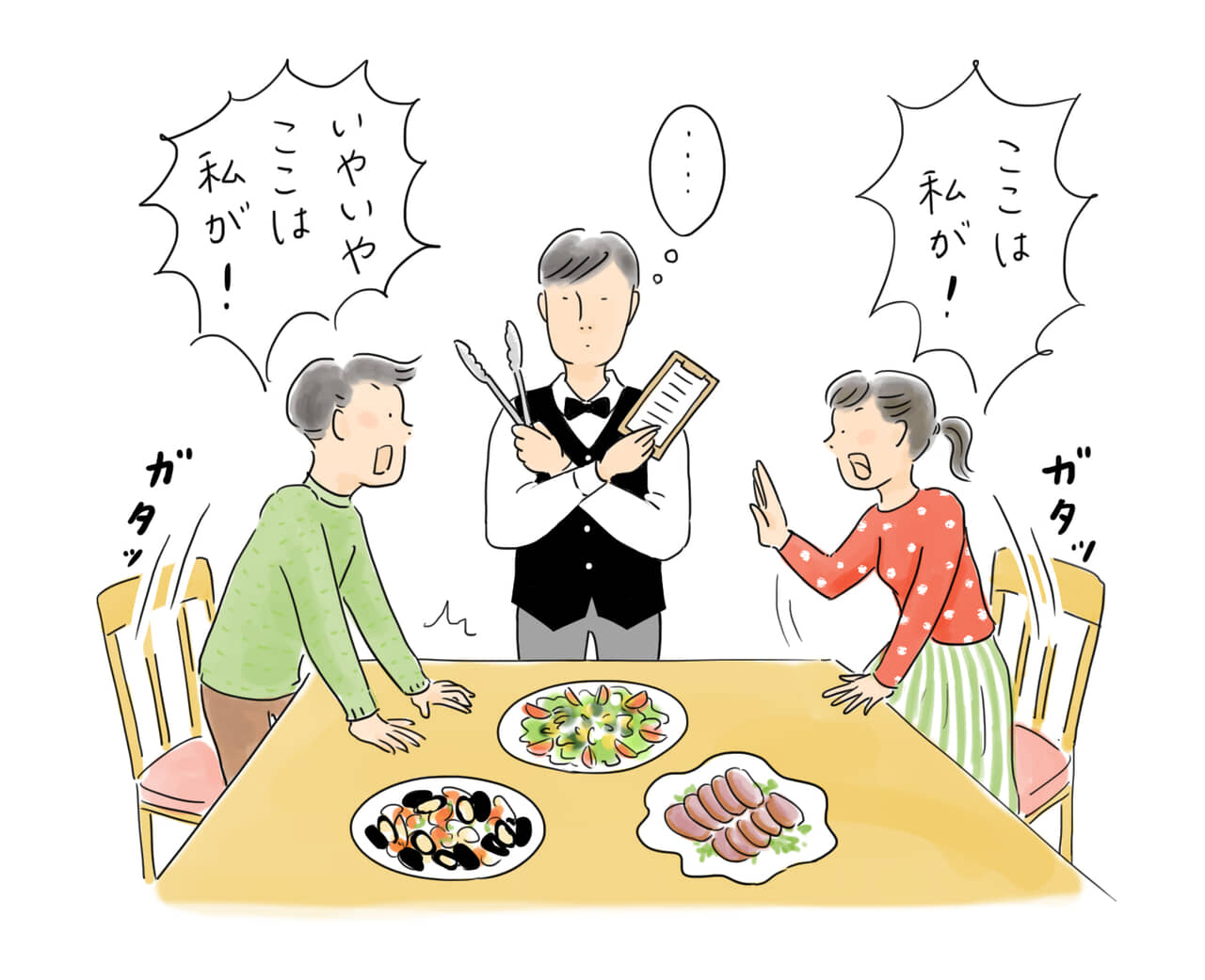「若さを失うことは、可能性を失うことか」 雨宮まみ『40歳がくる!』葛藤を強さにして生きた証【若林良】
■映画『生きる』を思わせる構成
『40歳がくる!』に話を戻すと、冒頭に述べたように、本書は後半においては、雨宮のはじめての担当となった編集者や、同世代で交流があったライターや劇作家などによる、それぞれの「雨宮まみ像」が語られる。
こうした構成に、黒澤明の映画『生きる』を連想した読者は、おそらく私ひとりではないだろう(……ないよね?)。『生きる』は、仕事への気力を失っていた中年の市役所員・渡辺勘治が主人公となる。彼は癌で死期を悟り、死ぬまでに自分にできることを見定め、その実現のために尽力することを決意するが、その時点で、がらりと物語の視点が変わる。続いては決意から半年ほどを経ての勘治の葬式のシーンとなり、彼の死期に随伴した同僚たちからの勘治の変化が語られる。それにより、単一の視点のみではない、より立体的な主人公の姿が浮き彫りになり、脚本を担当した橋本忍の言葉を借りれば、「複眼の映像」の豊かさがみなぎった作品となっている。この豊かさは、『40歳がくる!』にも当てはめて考えることができるだろう。
『40歳がくる!』の場合、雨宮の死から少なくない年月が経過している以上、追悼の意味を込めて、その道のりに随伴した書き手による原稿も併録されることは、むしろ自然ではあっただろう。また、連載原稿だけではページ数が充分でないという物理的な問題もあったかもしれないし、出版社が『生きる』を意識したかと言えば、その可能性は考えにくい。さらには、こうした構成自体がそこまでもの珍しいわけではないだろうし、類似した構成の本もほかに多く見つけることができるだろう。
とはいえ、一度連想をしてみると、そこからさらなる連想を広げたくもなる。なので『生きる』とつなげての話を続けよう。『生きる』では、主人公の変化を目のあたりにした同僚たちは、通夜の席で次々に自分も生まれ変わったつもりで奮闘することを口にするが、一夜明けた職場では、相変わらずの右から左へのルーティンワークが繰り広げられる。もっとも主人公に共感を覚えていた若い職員はそんな職場に怒りを覚えたような反応を見せるものの、表立って主張をすることもできず、帰りの道のりで物憂げに町を見つめる。
この職員のように、亡くなった人の想いを受け継ぐことの難しさに突き当たりながらも、しかし自身への問いを続けること。そうしたことを考えた時に、本書の特別寄稿のなかでもっとも私の心に残ったのは、住本麻子による「雨宮まみと「女子」をめぐって」だった。住本は寄稿者のなかでは、唯一雨宮と直接の接点はなく(雨宮に認識をされてはおらず)、雨宮への強い思いは吐露しながらも、あくまでも第三者のスタンスは崩さず、雨宮のデビュー時におけるフェミニズムの潮流とその変遷、雨宮が牽引してきた「女子」文化について考察を深めていく。住本は、雨宮の死後におけるフェミニズムの隆盛によってさまざまな常識が変わってきている現在、その端緒になった存在ともいえる雨宮への批判は「可能だし、むしろ必要」と述べたうえで、しかし「わたし自身は「女子」を経由する以前に戻ることはできない」と、雨宮の存在がすでに自分と不可分な血肉となっていることを示唆する。
先人たちの残したものを、無条件に賞賛すべきとは私自身も思わない。『生きる』の場合、たとえばルーティンワークを続ける主人公に対して「彼には生きた時間がない」「死骸も同然」と喝破する冒頭のナレーションは、現在の視点からは多少の違和感が生まれるものかもしれない。生き方に「正解」をさだめ、それに沿って主人公の行動を論評するような姿勢にはある種のマッチョイズムが否めないし、日々の仕事に思うところはありつつも、なかなか自分を変えることができない同僚たちの姿に、むしろ人間らしさを感じる向きもあるだろう。